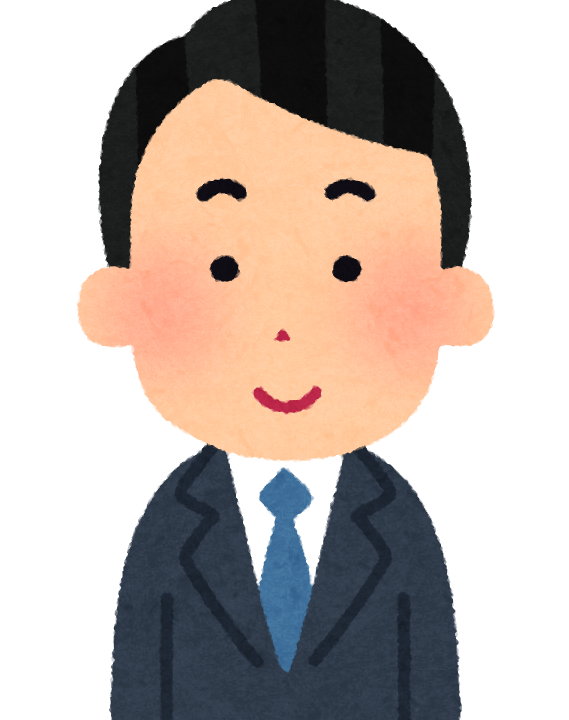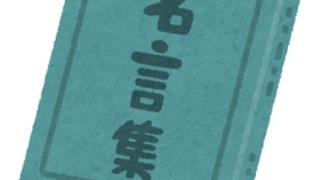発達障害の診断を受けたdobbyが「習慣化」の技術について書いていく記事となります。今回は習慣化に「囚われる」事象について、そのデメリットと囚われから解決する方法について、自分の考えを書いていきます。
「囚われ」とは
習慣化の「囚われ」について書いていく前に、そもそも「囚われ」という現象が何なのか書いていきます。辞書で引くと下記の意味が出てきます。
- つかまえられる。とらえられる。
- 固定した価値観や考え方などに拘束される。
ここでいう「囚われ」は②になります。
さらに「囚われ」という事象は森田療法にも出てきます。とらわれと執着 | こころのプラネット (cocoro2019.net)によると、「囚われ」は不安障害が起きる原因となる、特有の心理のメカニズムと解説されています。
習慣化の「囚われ」
習慣化に囚われるという事象は、「習慣化しようとしている行動や、すでに習慣化している行動を、『何が何でもやらなきゃいけない。』と考えて、他の事情を考慮せずに優先的にしてしまう。」 という事象であると私は考えます。
習慣化に「囚われる」デメリット
ここでは、習慣化に囚われるデメリットについて、あげていきます。
自己嫌悪に陥る
習慣化の「囚われ」が発生すると、その行動を「やらなきゃいけない」ものとして義務的に考えてしまいます。そうなると、何らかの事情で出来なかった場合、その事情を考慮せず「行動できなかった」自分を責めてしまい、自己嫌悪に陥ります。
達成感を感じない
習慣化の「囚われ」が発生すると、行動しても「義務でやった。」としか考えられ無くなります。今までできなかった行動をやっても、進歩したと肯定的に認識できません。 肯定的に認識できないことで、達成感を感じることも、達成した自分を認めることもできなくなります。
習慣化が定着しない
「出来ないと自己嫌悪」「出来ても達成感がない」状態で習慣化の行動を続けていても、苦しいだけです。結果として、自分の行動心理のハードルをあげてしまっています。
また、習慣化に「囚われる」と、行動のハードルを下げようとせず(下げることも自己嫌悪に陥ります)、しんどい行動を続けようとします。
その結果、習慣化したい行動を「面倒くさい」と感じるようになり、習慣化が定着しなくなります。
無理して行動する
習慣化に「囚われる」と、上記の「自己嫌悪に陥る」心理を避けようとして、無理してでも行動します。例えば「雨が降っていても、外に出てランニングする。」ということをしてしまいます。
優先事項を後回しにする
習慣化に「囚われる」と、「行動しなければ」ということにしか目が向かず、優先すべき事項があってもそれを差し置いて行動しがちになります。
本来の目的を忘れる
そして、習慣化に「囚われる」ことの一番大きなデメリットは、何のために習慣化の行動をしているのかわからなくなることです。
習慣化に「囚われる」と、「習慣化の行動をすること」自体が目的になってしまいます。
本来行動は目的を達成する手段であるものが、手段がいつの間に目的にすり替わってしまいます。
例として、「健康維持をする目的で運動を習慣化する。」ことをあげます。
でも、疲れているときに運動してもかえって健康を損ねますよね。
習慣化にとらわれてしまうと、運動すること自体が目的となります。
運動すること自体が目的になると、疲れていても無理して運動をしてしまいます。その結果かえって調子を悪くしてしまいます。こうなると、「健康になる」という本来の目的がいつの間にかなくなってしまい、本末転倒ですよね。
習慣化にとらわれない対策
結局、習慣化に囚われないためには、ある程度は「行動しなくていい。」と認めるいうことになります。当然、これは「習慣化の行動をしない」ということではなく、「無理を感じたら習慣化の行動を控える。」ということになります。その具体策としては以下のとおりです。
代替案を設定する
まず、習慣化の行動が無理と感じた場合、目的に沿った代替案を設定しましょう。
例えば、
- ハードな運動がしんどいと思ったら、散歩をする。
- ブログの記事が書けない時は関連書籍を読む。
という具合です。この時に、「本来の目的に沿っているか。」ということを念頭に置いて、代替案を考えましょう。
目的がはっきりしていれば、それに沿った代わり行動をすることで、「目的に役立つ行動をした。」ということで、満足感が得られると思います。
最低ラインを設定する
あとは、毎日必ずやるということではなく、週4日やるというように、目標よりは低いが「最低これだけはやっておく」ラインを設定しましょう。
その最低ラインはできるだけ守りましょう。「毎日は出来なかったけど、最低ラインを守った」ことで「次の週は毎日やろう」という習慣化への動機づけになりますし、「最低ラインを守った」という満足感も得られます。
もし、自ら決めた最低ラインすら守れない習慣化の行動であれば、むしろその行動があなたのやりたいことではないと思って、行動自体を見直しましょう。「自分のやりたいことに沿って、行動を見直す」というのも、目的に沿った立派な行動です。
結局、「無理しない」「たまにはやらなくてもいい」と思うことが、行動の習慣化にも、習慣化された行動の継続にもつながります。
まとめ ~囚われずに習慣化~
以上、習慣化の「囚われ」について書いていきました。まとめると、
- 習慣化に囚われると、習慣化の行動が定着しない、本来の目的に沿わなくなるなどのデメリットが有る。
- 代替案や最低ラインを設定して、「無理をしない」ことで習慣化の行動が継続する。
ということになります。
特に発達障害の特性、ASDの「こだわり」の特性が強く働くと、囚われる状態になりがちで、無理します。そうならないように、自分をコントロールしていきましょう。
最後に、リワークで「自分を全肯定する。」ことを行動目標にしている人が話していたことを紹介します。
その方は、「朝寝坊した時でも、『昨日疲れていて体調が悪かったから朝寝坊した。』という原因がわかってよかった。」というように「失敗しても肯定する」考え方を紹介してくれました。
もし、「囚われる」考え方だと「失敗した自分を否定する。」ことになりがちで、上記のような新たな気付きは得られないと思います。
なので「囚われずに習慣化」をしていきましょう。習慣化は大事ですが、くれぐれも「囚われ」て自分を苦しくしないでください。